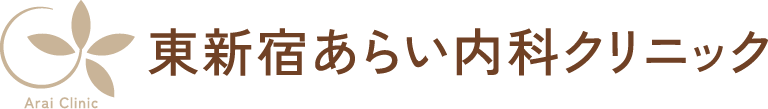当クリニックにおける生活習慣病の診療
生活習慣病の管理において重要なのは、きちんと検査をすることです。
理由としては痛みなどの症状がある場合、治療により症状がなくなれば効果が実感できますが、生活習慣病の場合、早期には自覚症状もほとんどないため病状を正しく理解するのが難しいからです。たとえば高血圧症で内服薬による治療をしており比較的コントロールが良くても知らぬ間にたんぱく尿が出現していたり、腎機能が低下していたりすることもあります。治療の目的は、脳血管疾患、心疾患、腎臓病などの合併症の進行を抑制することにあります。これらの疾患が進行していないかしっかりと検査を行い治療につなげていきます。当クリニックで行う検査については以下のようなものがあります。基本的に院内検査ですのですぐに結果を知ることができます。
血液検査
糖尿病の指標であるHbA1c、コレステロールや中性脂肪、腎機能の指標であるクレアチニン、尿素窒素などを定期的に確認します。
尿検査
たんぱく尿の有無や量などを定期的に確認します。
心電図検査
不整脈や心血管疾患の評価を定期的に行い、変化が無いか確認します。
レントゲン検査
心拡大や肺水腫などの有無や変化について定期的に確認します。
頸動脈エコー
首の血管である頸動脈の状態を調べる超音波検査です。動脈硬化の早期発見や進行具合を確認します。
血圧脈波検査
上腕と足首の血圧比(ABI)や脈波の伝わり方(PWV)を測定することで、血管の硬さや狭窄、閉塞の程度を調べます。血管年齢なども参考として得られます。
検査結果から将来起こり得るリスクを正しく評価し、患者さんに自分の病気のことを理解していただき、治療について一緒に考え薬だけでなく、生活習慣や栄養指導を含めたオーダーメイドの診療を行ってまいります。
糖尿病
糖尿病は糖をうまく細胞に取り込めなくなり血液中の血糖値が慢性的に高い値となる慢性病気です。大きく1型糖尿病と2型糖尿病に分かれており、糖尿病患者のうち95%は2型糖尿病で生活習慣病の一つとされています。発症には血糖値を下げる働きのあるインスリンの作用の低下や不足に加え、過食、運動不足、肥満、ストレスといった生活習慣が関係していると考えられています。
高血圧症
血圧とは、心臓から送り出された血液が血管(動脈)の壁を押す圧力を指し、心臓の収縮と拡張によって加わる力を表します。血圧値は「収縮期血圧(最高血圧)/拡張血圧(最低血圧)mmHg」と示されます。血圧の正常値は収取期血圧120未満、拡張期血圧80未満ですが、常に一定ではなく緊張や不安、運動、疲労、睡眠不足などストレスや環境、日内変動によっても変動します。高血圧症は、正常範囲よりも高い血圧が続く病態をいいます。高血圧の原因としては塩分過剰摂取、ストレス、運動不足、肥満、喫煙、加齢などの生活習慣や遺伝的要因などがあります。
脂質異常症
血液中には脂質として、コレステロール、中性脂肪、リン脂質、遊離脂肪酸の4種類があります。これらは体内で重要な役割を果たしていますが、多すぎると様々な問題を引き起こすようになります。この状態を脂質異常症と言います。「悪玉コレステロール」といわれるLDLコレステロールが必要以上に増えたり、「善玉コレステロール」であるHDLコレステロールが減ったりする病態は動脈硬化を引き起こします。脂質異常症は、それだけではとくに症状が現れることはありませんが、気がつかないうちに血管が傷つけられ、静かに動脈硬化が進行し、脳や心臓の疾患につながるおそれがあります。脂質異常症の主な原因は、食生活(肥満・カロリー過多)や過度な飲酒、喫煙、運動不足などが考えられます。治療は通常、食事療法と運動療法からはじめます。薬物療法は、これらを行っても脂質管理の目標値が達成できなかったり、持っている危険因子が多く、動脈硬化や動脈硬化による疾患を起こすリスクが高かったりする場合に開始されます。
高尿酸血症
高尿酸血症とは血液中の尿酸が7.0mg/dlを超える病態をいいます。尿酸値が高いだけでは症状はありません。尿酸値が高い状態が続くと尿酸は結晶化し関節などに蓄積していきます。そこで炎症が起き痛みを生じる疾患が痛風です。足の親指の付け根に生じやすく歩けないほどの痛みを生じることがあります。痛みに対しては消炎鎮痛薬が使用され、その後、尿酸値を下げる薬を内服します。尿酸はプリン体と呼ばれる物質から産生されるのでプリン体を多く含むビール、卵、魚卵、肉、魚などを多くとっている人は注意が必要です。また、腎結石、尿路結石の原因になるほか、肥満や高血圧、脂質異常症、糖尿病を複合的に合併していることも多いです。