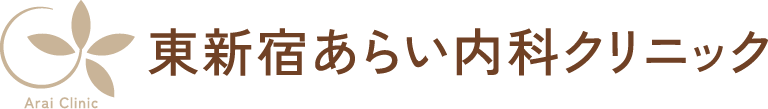高血圧は脳卒中、心疾患、慢性腎臓病の発症リスクを高めます。
血圧とは、心臓から送り出された血液が血管(動脈)の壁を押す圧力を指し、心臓の収縮と拡張によって加わる力を表します。血圧値は「収縮期血圧(最高血圧)/拡張血圧(最低血圧)mmHg」と示されます。血圧の正常値は収取期血圧120未満、拡張期血圧80未満ですが、常に一定ではなく緊張や不安、運動、疲労、睡眠不足などストレスや環境、日内変動によっても変動します。高血圧症は、正常範囲よりも高い血圧が続く病態をいいます。高血圧の原因としては塩分過剰摂取、ストレス、運動不足、肥満、喫煙、加齢などの生活習慣や遺伝的要因などがあります。
日本で高血圧の人は4,000万人以上、3人に1人は血圧が高いとされています。そのうちの7割は血圧を適正なレベルに管理出来ていないのが現状で、高血圧だと気づいていない、気づいているが治療を受けていない人も800万人以上もいます。血圧は徐々に変化していくので体が慣れてしまい自覚症状がない人がほとんどです。
血管の壁は本来弾力性がありますが、血圧が高い状態が続くと血管の壁が次第に厚く、硬くなります。これが高血圧による動脈硬化です。高血圧によってリスクが高くなるのが脳卒中や心疾患です。慢性腎臓病(CKD)の発症リスクも高まり、収縮期血圧が10mmHg上がると将来腎不全になるリスクが30%上昇するという研究報告もあります。

高血圧