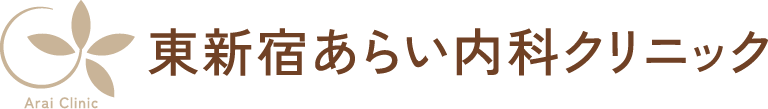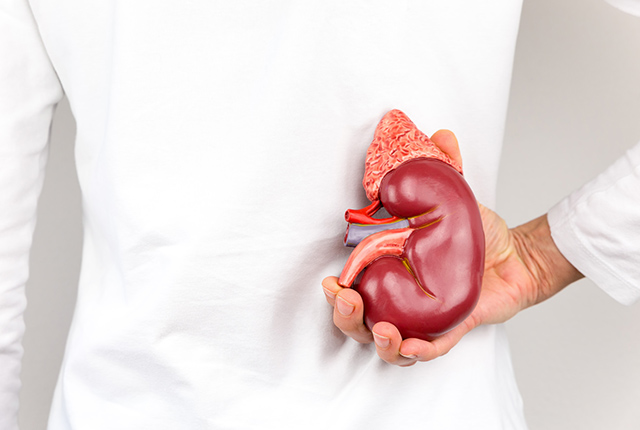慢性腎臓病(CKD)は腎臓の機能低下、尿検査異常(たんぱく尿、血尿)が3ヶ月以上持続する病態です。CKDは末期腎不全、心血管疾患、死亡などの重篤なリスク因子となりますが、初期は自覚症状に乏しく健診などで検査を受けないと見逃されてしまう病気です。2024年の推計では患者数は約2,000万人(成人の5人に1人)と言われております。
腎臓は老廃物や余分な塩分・水分を尿として排泄し、体内のバランスを維持するのに重要な役割を果たしており、それ以外にも血液を作る、カルシウムや骨代謝の調節など人間が生きていくために不可欠な臓器であるため、末期腎不全となると血液透析をはじめとする腎代替療法が必要となり日常生活に制限が生じることがあります。
当院HPコラム「あなたは大丈夫?慢性腎臓病(CKD)腎臓の役割について」でも詳しく説明しています。