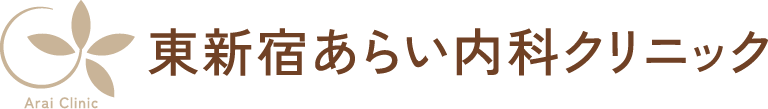2025年9月18日

片頭痛は遺伝的な背景を持つ、比較的よく見られる疾患です。発作時には強い痛みや感覚過敏などの症状が現れ、日常生活に大きな影響を及ぼすこともあります。最近の研究では、片頭痛にさまざまな共存症が伴うことが明らかになっており、これらの疾患が片頭痛の慢性化に関与する可能性も指摘されています。
このコラムでは、片頭痛と関連の深い代表的な共存症についてご紹介しながら、治療を行う際に意識しておきたいポイントを整理します。
片頭痛と脳・心血管疾患の関係
近年の疫学研究により、片頭痛が脳・心血管疾患のリスク因子であることが分かってきました。長期的なコホート研究では、片頭痛を持つ方に以下の疾患が多く見られる傾向が報告されています。
- 心筋梗塞
- 虚血性・出血性脳卒中
- 静脈血栓塞栓症
- 心房細動・粗動
特に「前兆を伴う片頭痛(migraine with aura:MA)」を持つ女性では、これらの疾患との関連がより強く示されています。複数のメタ解析によると、MA患者の虚血性脳卒中に対する相対リスクは1.56〜2.51とされており、「前兆のない片頭痛(migraine without aura:MO)」でも1.02〜1.83の範囲でリスク上昇が認められています。
また、45歳未満の女性や経口避妊薬を使用している女性では、脳卒中のリスクがさらに高まる可能性があることも示唆されています。
片頭痛と経口避妊薬の使い方
片頭痛を持つ女性がエストロゲンを含む経口避妊薬(combined oral contraceptives: COC)を使用する際には、脳血管イベントのリスクを踏まえた慎重な判断が必要です。
- 前兆あり片頭痛(MA):複数の研究で脳卒中リスクの上昇が示されており、COCの使用は原則として避けるべきとされています。国際的なガイドラインでも禁忌とされることが多いです。
- 前兆なし片頭痛(MO):MAに比べてリスクは低いものの、完全に安全とは言えません。特に35歳以上の女性、喫煙者、その他の血栓リスク因子がある場合は、低用量エストロゲン製剤(例:20μg以下)やプロゲスチン単独製剤(ミニピル)などの選択肢を検討することが望ましいです。
いずれの場合も、ピルの使用開始後は定期的な経過観察が重要です。片頭痛の性状や頻度の変化、神経症状の有無などに注意を払いながら、安全性を確認していく必要があります。
その他の疾患との関連と治療上の注意点
脳出血との関連については、肯定的な報告と否定的な報告が混在しており、現時点では明確な結論は出ていません。一方、心筋梗塞に関しては、片頭痛患者の相対危険度が1.12〜1.23と報告されており、片頭痛が心疾患の直接的な原因なのか、それとも他の危険因子の指標なのかについては、今後の検討が必要です。
治療においては、心血管疾患を併発している患者さんに対して薬剤選択に注意が必要です。血管収縮作用を持つトリプタン系薬剤は使用が制限されることがあり、代替として血管収縮作用を持たない5-HT1F受容体作動薬「lasmiditan」が選択肢となる場合もあります。
片頭痛と精神疾患のつながり
〜共存症への理解と治療のヒント〜
片頭痛は、強い痛みだけでなく、精神的な不調とも深く関係していることがわかってきました。実際に、片頭痛を持つ方の中には、うつ病や不安障害などの精神疾患を併せ持つケースが少なくありません。特に、月に14日以上片頭痛があるような慢性化した状態では、こうした精神的な症状の頻度も高くなる傾向があります。
このような関連には、脳の働きや神経伝達物質の変化が関係していると考えられています。
- 片頭痛の発作時には、血液中のセロトニンという物質が一時的に増加し、発作がない時期には減少することが知られています。
- セロトニンは気分にも深く関わる物質で、うつ病の方でも同様の変動が見られることがあります。
- また、うつ病を伴う慢性片頭痛の方では、脳内の**GABA(ガンマアミノ酪酸)という抑制性の神経伝達物質が少なくなっているという報告もあります。
不安障害との関連
不安障害との関係も見逃せません。片頭痛のある方は、全般性不安障害やパニック障害を持っている割合が、そうでない方に比べて約10倍高いとされています。こうした精神的な症状が片頭痛の頻度や重症度に影響を与えることもあり、早期に気づいて対応することが重要です。
治療と管理のポイント
精神疾患との共存は、薬剤使用過多による頭痛(medication-overuse headache:MOH)や慢性片頭痛(chronic migraine:CM)のリスクを高めることが知られています。つまり、精神的な不調が片頭痛の慢性化や治療抵抗性に関与する可能性があるため、早期の介入と包括的な管理が求められます。
頭痛外来や精神科、心療内科などの連携も視野に入れながら治療方針を検討していくことが望まれます。
文責:東新宿あらい内科クリニック 副院長 新井祐子(日本神経学会専門医)