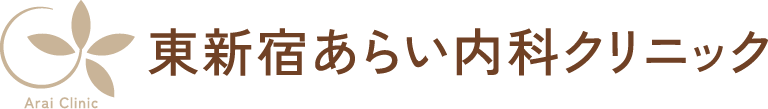2025年10月24日

慢性腎臓病(CKD)の患者数は?
2024の推計では日本における慢性腎臓病(CKD)患者数は約2,000万人(成人の5人に1人)といわれており2022年末、腎代替療法として透析を行っている患者数は約35万人に上ります。決して他人ごとではなく誰もが患者となる可能性がある病気です。
腎臓は何をしている臓器なの?
腎臓はソラマメのような形をした臓器で握りこぶしくらいの大きさ(120g程度)、腰のあたり後腹膜腔という場所に右と左に1個ずつあります。腎臓の働きは尿を作り老廃物を排出するだけでなく様々な働きをしています。今回は腎臓の働きについて説明します。
老廃物の排泄
腎臓は糸球体や尿細管などによるネフロンとい機能単位が集まって出来ている臓器であり片腎で100万のネフロンが存在します。尿を生成する過程は糸球体でのろ過、尿細管での再吸収が重要な役割を果たします。糸球体ろ過量は毎分100ml、ろ過される血液は1日でおよそ144L程度となり、そのうちの99%が再吸収され1.4Lが最終的な尿となります。糸球体ろ過量を直接知ることは難しいため、血液検査でわかるクレアチニン値と年齢・性別から推算した推算糸球体ろ過量(eGFR)を使用します。これを腎臓の老廃物を尿に排泄する能力として慢性腎臓病の診断や重症度の分類に利用しています。eGFRが低下すると尿毒症という老廃物や有害物質が蓄積することで起こる様々な症状を呈するようになります。
水分・塩分・血圧の調節
ヒトの体は60%が水分で構成されています。体内の水分量を調節するホルモンとして抗利尿ホルモン(ADH)がありますが、これは脳の視床下部で産生され下垂体後葉から分泌され、腎臓に作用し水の再吸収を促進し、体内の水分量を調節する働きがあります。水に関する腎の調節能は理論上0.5Lから30Lの間で尿量により調節しています。また、血圧や塩分(ナトリウム)・体液量の調節をする代表的なホルモン系にレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系(RAA系)があります。腎臓からレニンが分泌され、このレニンがアンジオテンシノーゲンをアンジオテンシンIに変換し、さらにアンジオテンシンIIへと変換されます。アンジオテンシンIIは、血管を収縮させて血圧を上げるとともに、副腎に作用してアルドステロンの分泌を促します。アルドステロンは、腎臓でのナトリウムと水の再吸収を促進し、結果として血圧を上昇させることになります。高血圧や心不全などの慢性的な疾患では、RAA系が過剰に活性化し、心臓や血管の肥大、線維化などを引き起こし、病態を悪化させることもあります。そのためRAA系に作用する降圧薬をはじめ様々な薬が使用されています。
電解質の調節
腎臓は、尿細管での再吸収と分泌を調節することで、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどの電解質バランスを保ちます。前述したRAA系などのホルモンが電解質バランスの維持にも重要な役割を果たしています。慢性腎臓病などの腎機能が低下した患者さんでは高カリウム血症に特に注意が必要です。カリウムは神経伝達や心筋の収縮に不可欠ですが、過剰にあると不整脈などの危険な状態を引き起こす可能性があります。また、酸化マグネシウムは緩下剤としてよく使用される薬ですが腎機能が低下した方が過剰に長期使用された場合、マグネシウムが過剰となり高マグネシウム血症をきたすこともあり注意が必要です。マグネシウムは通常の食事をしている健康な方であれば不足することはありません。また、マグネシウムはカルシウムと拮抗的に働くので心疾患の予防の観点からカルシウム摂取量の半分程度が理想と言われています。
酸塩基平衡の調節
酸塩基平衡とは、体の中の酸性物質とアルカリ物質のバランスのことで健康なヒトの血液はpH値が約7.35~7.45の弱アルカリ性に保たれており、この範囲を維持するしくみ全体のことを指します。このバランスが崩れると、アシドーシス(酸性に傾く)またはアルカローシス(アルカリ性に傾く)と呼ばれる状態になり、全身の臓器に影響を及ぼします。肺による調節と腎臓による調節があり腎臓は酸性の過剰な水素イオンを尿中に排泄し、重炭酸イオンを再吸収することで酸を中和します。pHの変化に応じて調整していますが、腎機能が低下すると代謝性アシドーシスという病態となり吐き気、疲労感、頭痛、意識障害があらわれることもあります。
造血調節
腎臓はエリスロポエチン(EPO)という造血に関連するホルモンを分泌します。慢性腎臓病のステージが進むと腎性貧血という病態になります。機序として腎臓からのEPOの相対的産生低下、骨髄における赤血球造血の抑制、赤血球寿命の短縮、鉄代謝障害、栄養障害などが考えられます。腎性貧血はQOLの低下、心血管イベント、入院リスク、認知機能障害、生命予後などと関連し臨床上重要な問題となります。以前はEPOを注射で補充する治療が一般的でしたが、現在は経口投与が可能な低酸素誘導因子プロリルヒドロキシラーゼ(HIF-PH)阻害薬が使用可能となり、腎性貧血の選択肢が広がっています。HIF-PH阻害薬は内因性のエリスロポエチンの産生を促すほか、体内の鉄利用効率の向上が期待されます。
骨代謝ミネラル調節
腎臓は、体内のカルシウムやリンといったミネラルのバランスを調整する重要な働きを担っています。しかし、慢性腎臓病(CKD)が進行すると、こうしたミネラルの代謝や骨の健康に異常をきたすことがあり、この病態は「ミネラル・骨代謝異常(Mineral and Bone Disorder)」と呼ばれ、略してCKD-MBDと表現されます。CKD-MBDは、腎機能の低下によってリンの排泄がうまくいかなくなったり、カルシウムの吸収に必要な活性型ビタミンDの産生が障害されたりすることで起こります。さらに、副甲状腺ホルモン(PTH)の調節にも異常が生じ、これらの変化が複雑に絡み合うことで、血液中のリンが過剰になる高リン血症や、カルシウムが不足する低カルシウム血症、骨がもろくなる骨脆弱化、そして血管にカルシウムが沈着する血管石灰化など、さまざまな異常が引き起こされます。これらの異常は、骨の健康だけでなく、心臓や血管にも深刻な影響を及ぼす可能性があり、心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患のリスクを高めることが知られています。そのため、CKD-MBDの管理は、こうした重篤な合併症を予防し、患者さんの生命予後を改善するうえで非常に重要です。